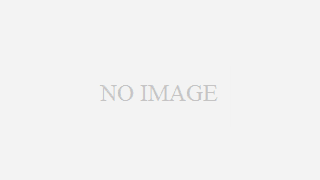 育て方に関する用語
育て方に関する用語 強剪定の基礎知識と実践方法
強剪定の効果と目的強剪定は、樹木の生育や樹形をコントロールする目的で行われる剪定方法です。強剪定を行うことで、樹木の枝数を減らし、日当たりや風通しを良くすることができます。また、強剪定を行うことで、樹木の成長を抑制し、樹形を整えることができます。強剪定は、樹木の生育や樹形をコントロールする目的で行われる剪定方法です。強剪定を行うことで、樹木の枝数を減らし、日当たりや風通しを良くすることができます。また、強剪定を行うことで、樹木の成長を抑制し、樹形を整えることができます。強剪定は、樹木の生育や樹形をコントロールする目的で行われる剪定方法です。強剪定を行うことで、樹木の枝数を減らし、日当たりや風通しを良くすることができます。また、強剪定を行うことで、樹木の成長を抑制し、樹形を整えることができます。